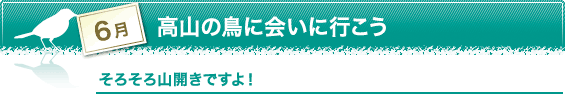
もう、皆さんの周りではツバメが巣を作り、子育てを始めているのではないでしょうか。ちょっと近くの山に出かけると、オオルリやキビタキの美しい声を聴くことができるでしょう。ふと目を遠くにやると、高い山の雪も解け始め、日本アルプスなどの高山ではそろそろ山開きをむかえるころになりました。今回は、これからの時期に高山に行くと見ることのできる鳥たちを紹介します。

本州では、標高1500mから2500m付近でオオシラビソやシラビソ、コメツガなどの針葉樹林が生育している地域を亜高山帯と呼びます。さらに標高が高くなると、高い木はなくなり、膝ぐらいの高さのハイマツが生育する高山帯になります。このような、亜高山帯や高山帯といった高い場所にまで来ると、普段私たちが生活している場所にはいないカラスを見ることができます。

カラスというと、市街地でよく見かけるハシブトガラスや、ハシボソガラスといったあの黒いカラスを思い浮かべる人も多いと思いますが、高山帯でよく見かけるのはホシガラスです。翼と尾は青みをおびた黒色ですが、体は全体的に茶色で細かい白い斑が星のように入っていることから「ホシガラス」という名前が付いたといわれています。町で見かける黒いカラスよりも体は小さく、鳴き声は「カーカー」ではなく、しわがれた声で「ガーガー」と鳴きます。

好物はハイマツの実で、秋に実が熟す頃にはハイマツ林によく現れます。カケスなどのように食べ物を貯蔵する習性があり、冬に雪が積もりにくいような場所にハイマツやブナの実をため込みます。このような行動がハイマツの種子の分散に一役かっているようです。高山にはゴミ集積所もありませんから、都会のカラスとは違って、ゴミを集団であさるようなことはありません。冬になると、雪を避けるように亜高山帯の少し下に移動しますが、低山帯や平野にまで降りて来ることはほとんどないようです。

高山にある登山道や、山小屋の周りの岩場を見ていると、岩にとまってヒバリのように、賑やかにさえずっている鳥を見かけます。その名もイワヒバリ。名前にヒバリと付いていても、こちらは麦畑などで見かけるヒバリとは違う仲間です。このヒバリとイワヒバリ、大きさはほぼ同じ、見た目には茶色が基調で賑やかな声で鳴くなど、似ているような気がしますが、ヒバリはヒバリ科、イワヒバリはイワヒバリ科で、分類学的には異なります。


イワヒバリは協同多夫多妻という、ちょっと変わった繁殖をします。これはオス4羽、メス3羽程度のグループをつくって、群れ以外の侵入個体に対しては群れのなわばりを守ります。また、その群れのメスは同一グループの複数のオスと頻繁に交尾をして、オスは交尾した複数のメスのヒナの子育てを手伝うというものです。5月の下旬になるとメスの総排泄腔(交尾時に精子の受け渡しのために接する部分)は円柱状に10mm程度突出して赤く肥大し、これをオスに見せつける独特のディスプレイ(求愛行動)をします。この求愛期間はおよそ1カ月続くようです。
冬になると、イワヒバリは標高の低い山地に移動します。標識調査によると、繁殖期に乗鞍岳で足環を着けた個体が、越冬期に栃木県足尾町、愛知県豊根村(豊根ダム)、奈良県川上村、山梨県河口湖町(御坂峠)で確認された記録があります。高い山まで行かなくても、冬であればイワヒバリは近くの低山でも見られるかもしれません。
高山帯のハイマツ林にはイワヒバリの仲間でカヤクグリという鳥がいます。岩場やガレ場の多い場所にはイワヒバリがよく見られますが、ハイマツなどの低木の多い場所ではカヤクグリがよく見られ、どうやら棲み分けているようです。 カヤクグリはイワヒバリよりもひとまわり小さく、背中側がチョコレートを思わせるこげ茶色で腹側は灰黒色の鳥です。一見地味ですが、鳴き声は鈴を鳴らしたように「チュリリチュリリヒリヒリ」と聞こえます。

こちらもちょっと変わった繁殖形態で、一妻二夫と考えられています。交尾のときに、メスは尾羽を水平に伸ばして細かく震動させ、イワヒバリと同様に赤く肥大した総排泄腔をオスに見せつけるディスプレイをします。 冬には低山や平地に移動して草むらの中で採食します。このことから、カヤクグリ(「萱潜」若しくは「茅潜」)の語源となっているようです。
高山帯の鳥で最も有名なのはライチョウではないでしょうか。ライチョウは北半球の高緯度地域に広く分布して、世界中に23亜種が知られています。日本にいるライチョウはその中の1亜種(Lagopus muta japoinca)で、世界的には分布域の南限に当たります。日本では、


繁殖は基本的に一夫一妻でなわばりをつくります。オスはなわばりに他の個体が入って来ないように、視界の開けた岩の上などに長時間とまって見張りをします。このため、いつも見張り場に使う岩の上にはたくさんの糞がたまっています。 巣はハイマツの枝の下の地上につくり、4~8個の卵を産みます。孵化したヒナは羽毛が乾くとすぐにメス親と共に巣を離れてしばらくは家族で行動します。この時期は、親子がお花畑で一緒に歩きながら採餌している姿をよく見かけます。

ライチョウは寒冷地の生息に適応しており、脚には羽毛が生えています。学名のLagopusはLagos(ノウサギ)、pous(足)という語が合わさり、足の特徴を表したものです。 ライチョウは、地球全体が寒冷で、日本が大陸と陸続きであった最終氷期に、大陸から渡ってきました。氷期が終わり、低地の気温が上がってきたときに、より寒冷な高山帯に生息場所を移していき、生き残ってきた種と考えられています。繁殖期には、高山帯のハイマツなどの生える標高の高い地域で生息し、積雪期になってもそれほど標高の低いところには降りず、雪の中にもぐって休息することもあります。このように寒冷な環境を好むライチョウにとって、地球温暖化が進むと高山にさえ生息することができなくなるのではないかと危惧されています。
ライチョウは天敵となる猛禽類を避けるために、朝夕の薄暗い時間帯に活発に動きますが、霧の濃い時や悪天候時などには昼にもよく出現します。天敵としては他にもオコジョやテンなどがおり、卵やヒナも狙われます。また、最近では低山で個体数が増えたシカが高山帯にまで侵入して、高山帯のお花畑などライチョウの生息環境を破壊してしまうのではないかと心配されています。
| ライチョウのオスとメス。オスが警戒するなか、メスは採餌(富山県立山町 撮影/安齊友巳) |
今から30年前に日本には約3000羽生息していたと推定されていましたが、近年では1700羽にまで減少したと推定されたため、環境省レッドリストではこれまで絶滅危惧Ⅱ類とされていましたが、2012年の見直し時に、より絶滅の危険性の高い絶滅危惧ⅠB類にランクが引き上げられました。その後保護増殖事業が開始されて、現在では野外での保護の取り組みの他、いくつかの動物園でスバールバルライチョウという日本のライチョウとは別の亜種で飼育繁殖が行われ、今後行われる日本のライチョウの飼育に向けた取組も行われています。
サントリー世界愛鳥基金では、【神の鳥「雷鳥」を次世代に引き継ぐために~ニホンライチョウの域外保全に向けた飼育繁殖技術の確立~】に助成(2015年度)をしています。
欧米などではライチョウの仲間の多くが狩猟対象となっていることから、人が近づくと警戒してすぐに逃げてしまいます。ところが、日本では古くから山岳信仰によって高山という山奥は神の領域で、そこに生息するライチョウは長い間「神の鳥」としてあがめられ、大切に守られてきたことから、いまでも登山客がすぐ近くを通っても全く驚かずに平然としています。ライチョウとのこのような関係が、これからも長く続くことを願います。

