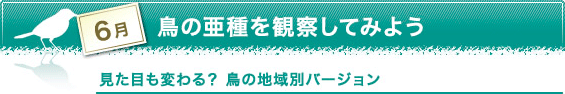
鳥業界だけでなく,バードウォッチングをしない人にも人気の鳥「シマエナガ」。このシマエナガを図鑑で探すとすぐ見つからないことがあります。よく探すとエナガの項に載っているのですが,見出しとなっているのは「エナガ」です。これはシマエナガが「種」ではなく「亜種」の扱いになっているからです。ではこの亜種とは何でしょう?


「亜」という漢字には「何かに次ぐもの」「似ているけれど本流とは違うもの」という意味があります。つまり亜種とは「種に次ぐもの」「種に似ているけれど違うもの」となります。この亜種の話をする前に,そもそも種について考える必要があります。実はこの「種とは何か?」という問いの答えは例えば「互いに交配できない単位を別種とみなす」などいくつかあり,そしてそれぞれの答えには例外があるなど,生物学者によってさまざまな見解があるという難しい問題です。ひとまずここでは「形態によって区別できること」を種の基準としましょう(分類学的種)。これは図鑑などの「エナガ」「コゲラ」「カルガモ」といった見出しともリンクしているので,わかりやすい基準です。
そして亜種とは「形態はある程度違うけど,別種にするほど違わない」という分類です。あとで話題にしますが,亜種にするか別種にするかの基準は固定されたものではないので,ややあいまいともいえます。また亜種にはもう1つ「分布域が異なる」という基準もあり,例えば日本本土と南西諸島といった,地理的に離れている2つの生物のグループがあり,それらが別種にするほど違わなければ亜種に分けることがあります。冒頭で挙げたシマエナガの場合,「エナガと別種にするほど特徴の差はなく,また分布が北海道に(ほぼ)限定されてエナガと分かれているので亜種」ということになります。


分類に関する小難しい話は抜きにして,亜種を観察することは何がおもしろいのでしょう?その1つが「ご当地バージョン」の観察です。亜種の基準である「分布域が異なる」に注目すると,例えばふだん見慣れたキツツキの仲間のコゲラでも,現在の分類では10もの亜種に分かれています。北海道,伊豆諸島,奄美群島,沖縄諸島,八重山諸島など,地域ごとに亜種がいるので,ご当地の鳥として改めて観察する楽しさがあります。亜種の中には日本本土と形態の差があまりない場合がある一方,中には「これは本当に別種ではないの?」と思うくらいに見た目が違う亜種もいます。これにはおもしろい法則があって,南の亜種は色味がどんどん濃くなり,北の亜種は逆に明るくなることがあります(グロージャーの法則)。また身近な鳥の1つであるヒヨドリも8亜種いますが,渡りをする亜種の翼は細長く,しない亜種の翼は幅広いといった違いもあります。見た目ではわかりづらいですが,こうした生態の違いを観察することもおもしろさの1つといえるでしょう。










そして亜種をしっかり意識して観察する大きなポイントの1つが,「亜種が別種になることがある」という点です。この文章の前半で「亜種にするか別種にするかの基準は固定されたものではない」と書きました。しかし近年,鳥の世界ではその基準が固定されつつあります。なぜなら分類の世界にゲノム解析,つまりDNAが用いられるようになったからです。今現在別種として分けられている種のDNA(ミトコンドリアDNA)を解析してみると,その多くは2%を超える違いがありました。この基準を当てはめると,亜種同士でもDNAに2%を超える違いがあれば,別種とみなせるという話になります。こうした基準で分類を見直してみると,これまで亜種とされていたものが別種となるケースが出てきました。実際,2024年9月に発行された「日本鳥類目録第8版」では,日本の鳥として新たに追加された36種のうち,9種は以前は亜種扱いだったものが個別の種に格上げされたものでした。鳥自体が変わったのではなく,分類という「物差し」が変わったことで種が増えたといえます。
具体例としてキビタキとリュウキュウキビタキを挙げましょう。両者はこれまで(目録第7版まで)は亜種同士でしたが,今回の改訂で別種同士となりました。例えば奄美大島でリュウキュウキビタキを見つけたとき,亜種だからと観察をおろそかにしてしまえば,せっかく今回の改訂で両者が別種となったことで,見た鳥のリストが1種増えるのに,その機会を失います(しかもリュウキュウキビタキは日本固有種)。 もちろん観察の熱量は亜種かどうかで決まるものではありませんが,せっかく亜種という分類単位が設けられているのであれば,その違いを意識することも,バードウォッチングのちょっと深い楽しみ方ではないでしょうか?





