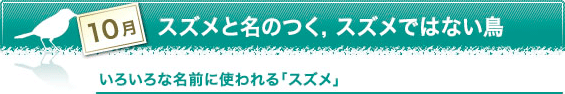
前回のお話は「スズメ」でした。日本で見られる「真のスズメ=スズメ科の鳥」はスズメ,ニュウナイスズメ,イエスズメの3種類です。しかし,カタカナの和名表記以外に目を向けてみると,実に多くの鳥が「スズメ」であることがわかります。今回はこうした「スズメじゃないけどスズメの名をもつ鳥」を紹介しましょう。


スズメは漢字で「雀」と書き,訓読みは「すずめ」,音読みは「ジャク,サク」です。漢和辞典によるとこの漢字は「小」「隹」の2つに分離し,「隹(ふるとり)」は鳥を表す部首なので,小さい鳥という意味の漢字になります。さて,鳥の図鑑の中にはカタカナ表記の種名やラテン語表記の学名のほかに,漢字での表記が載っているものがあります。今回,日本の鳥で雀という漢字を使う,スズメ科以外の鳥がどのくらいいるかを調べてみました。わかりやすいのは訓読みの「すずめ」をそのまま使うパターンで,具体的にはウミスズメ(ウミスズメ科)やゴマフスズメ(ホオジロ科),ベニスズメ(カエデチョウ科 ※外来種)などが挙げられます。中でもウミスズメはその科の中で小さい種を指すことに由来するなど,体が小さいことから「スズメ」の名を付けたと思われます。
では音読みの「ジャク」はどうでしょう。こちらはヒレンジャクとキレンジャクのレンジャク科の2種がいます。漢字表記では「緋連雀」「黄連雀」で緋と黄は体色,連雀は「数多く連なる小鳥」を表しています。この2種はしばしば大群を作り,ヤドリギなどの木の実を集団で食べる様子が観察されます。こうした生態を示すために「雀」の漢字をあてたのでしょう。このほかにもクジャク(※外来種)も漢字では「孔雀」と書きます。




図鑑を見ていくと,意外にたくさん「雀」の漢字が登場するのに気づきますが,その多くは先ほど挙げた音訓読みを使いません。例えばヒバリ(ヒバリ科)は「雲雀」と書きますが,これは熟語単位で訓読みを当てたもので熟字訓といいます(鳥以外のわかりやすい例:梅雨(つゆ)や今日(きょう)など)。鳥における雀の多くはこの熟字訓としての使い方で,ほかにもシジュウカラ(四十雀)やヤマガラ(山雀)などのシジュウカラ科の鳥も挙げられます。カラはもともと小形の鳥を指す言葉ですが,雀には本来「カラ」という読みはなく,小さい鳥の代表として雀の漢字を使ったのでしょう。ちなみに〜ヒバリや〜カラは分類の違う鳥の種名にも使われることが多く,例えばセキレイ科のタヒバリ類やシギ科のヒバリシギ,ゴジュウカラ科のゴジュウカラやカモ科のシジュウカラガンも「雀」が使われ,結果として分類をまたいだ多くの鳥に漢字の雀が登場するのです。
また熟字訓の別の例として,小形のタカ類であるツミの漢字表記「雀鷹」があります。ツミは雄がヒヨドリ程度の大きさと,タカ科では最小の部類に入る鳥なので,こちらも「小さい鷹」を意味する漢字表記となったのでしょう。なお,英語表記も「Sparrowhawk」で直訳すればスズメダカとなります。






こうして見ていくと,スズメの名前がついたり,漢字の雀を使う鳥はスズメ科以外に日本では13科にも及びました。スズメそのものも日本人にとって最も身近な鳥の1つですが,それだけにほかの鳥の名付けにも多く使われたことがわかります。
さらにユニークな例として,鳥以外の生物に「スズメ」が用いられることが少なくありません。ただし,鳥類では「スズメ」は小さいことを示すことが多いのに対し,昆虫,魚,植物は示すことが変わることが多いようです。例えば「スズメバチ(雀蜂)」では,「体が大きいこと」や「巣の模様がスズメの模様に似ている」ことが名前の由来という説があります。ほかにも夏〜秋にかけて花の周りを活発に飛び回る,透明な翅をもつちょっと大きめの黄緑色の昆虫を見たことはないでしょうか? 一見ハチのように見えますが,これはガの仲間のオオスカシバという昆虫で「スズメガ科(雀蛾科)」に属します。スズメガ科は日本に80種ほどいますが,「〜スズメ」「〜ホウジャク(蜂雀)」という種名が多く,高速で飛ぶことが特徴の1つで,スズメの名も「スズメのように活発に飛び回る」に由来するとされます。
海の中にもスズメがいます。温帯や熱帯の浅い海を中心に生息する「スズメダイ科」の魚は木の葉のような形の小形魚で,よく知られるクマノミなども属するグループです。青や黄色のカラフルな種類も多く,水族館や観賞魚としてもおなじみの魚ですが,スズメの名をもつ由来には諸説あって,まず「スズメのように小さい」こと,加えて「スズメのように群れる」こと,変わったものに「目がスズメに似ている」があります。
ここでは紹介しませんが,植物にもスズメの名をもつ種類がありますし,ほかにどんな「スズメ」がいるのか,探してみるのも楽しいかもしれませんね。



