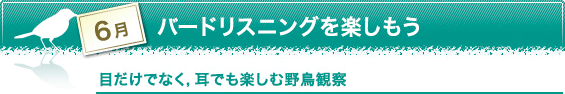
バード“ウォッチング”というように,野鳥観察は基本的に目で楽しむものです。しかし,実際の探鳥ではさまざまな音を聞くことで,鳥の居場所だけでなく,その鳥が何をしているのかということまでわかってしまうこともあります。鳥が発する音声を活用することで,バードウォッチングをより深く楽しめるのです。
*この後紹介される鳥の種名のリンク先で声を聞くこともできます。


鳥が発する音声として真っ先に思いつくのは「鳴き声」でしょう。鳥は声でさまざまなコミュニケーションを取りますが,大きく「さえずり」と「地鳴き」に分かれます。さえずりは主に繁殖にかかわる声で,その役割はつがい相手への求愛やライバルに対する威嚇(なわばり宣言)などが挙げられます。一般的に「鳥のきれいな声」とされるのはさえずりのほうで,鳥によっては非常に複雑な節回しの長いさえずりを発し,それは時に「歌」とも表現されます。繁殖にかかわる声なので,一部の鳥を除いて成鳥オスが発し,聞こえる時期も春の繁殖期の短期間に限られます。
観察という視点でさえずりを聞くと,繁殖目的なので発する対象は同じ種であり,それを利用すれば種の識別に使えます。実際多くのバードウォッチャーは,姿を見つけるよりも先にさえずりを聞いて種を識別し,探すのに役立てます。例えば聞こえてきたさえずりがオオルリだとわかれば,オオルリはよく枝先でさえずる鳥なので枝先を中心に探してみる,といった具合です。




もう1つの地鳴きは簡単にいえば日常会話に使う声です。例えば仲間に対して危険を知らせる,移動の合図を送るといった場面で発せられ,季節や性別,成鳥か幼鳥かを問わず発する声です。そして多くの地鳴きはさえずりとは異なり,「チッ」や「チャチャッ」といった短くてシンプルな声です。また,声を発する対象も同じ種とは限りません。例えば秋冬の林でよく見られるカラの混群はシジュウカラやエナガ,メジロなど複数種の鳥が混じっていますが, そこで発せられる地鳴きは自分とは異なる種にも情報を伝達します。食物を探したり,外敵から身を守るといった群れ全体の利益になることを伝えるのであれば,種を越えた共通の言語があったほうが便利です。
地鳴きは「短くてシンプルな声」「他種にも情報を伝える」という特性があるため,観察という視点で聞くと,種類の識別はさえずりに比べて難しく,鳥がどこにいるかを探るヒントに使うことが大半です。しかし最近の研究では,シジュウカラは複数の地鳴きを組み合わせて仲間に「タカが来た,警戒して!」などの情報を伝達していることがわかっています。こうした声の機能がもっとわかってくれば,観察している鳥がどんな行動をしているのか,あるいはほかの種の鳥との関係が見えてくるかもしれません。




ここまで紹介してきたさえずりや地鳴きはいわゆる「声」ですが,鳥が発する音にはほかにもいろいろあります。まずはキツツキが木を叩く時に出す「ドラミング」と呼ばれる音はさえずりと同じような機能があるとされます。アカゲラやアオゲラといった中形のキツツキでは1秒間に20回というものすごいスピードで木を叩くため,遠くからでもよく聞こえてきます。こういったドラミングだけでなく,巣作りや採食の際にも木をつつくことがよくあるため,林の中で聞こえてくる「コツコツ」という音はキツツキがいることを教えてくれます。同じく嘴で発する音に「クラタリング」があります。上下の嘴をたたき合わせることで,「カタカタカタ」と聞こえる,コウノトリが出す独特の音声で,仲間同士でのコミュニケーションや威嚇に用いられます。
少し変わった音に「羽音」があります。鳥が羽ばたくとき羽が空気を切ることで音が出ることがあり,身近な鳥では翼が大きく,羽ばたきもしっかりしているカラスで羽音が聞こえることがあります。羽音を求愛に使う例もあり,身近なところではキジのほろ打ちが有名です。また,夏に日本の高原に飛来するオオジシギというシギの仲間も羽音を求愛に使います。この鳥のディスプレイフライトはユニークで,飛びながら鳴き,上空で尾羽を広げ,急降下しながら「ザザザザザ」という羽音を出します。その音の大きさからオオジシギは「カミナリシギ」という異名があるほどです。





