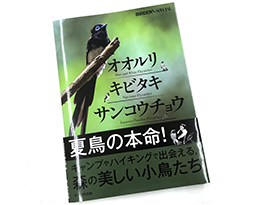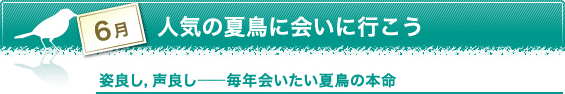
長かった冬が終わり,春が訪れると,生物の活動は一気に活発になります。鳥の世界でも冬鳥たちが北へと移動し,代わって南から夏鳥が日本に飛来してきます。夏鳥といえば有名なのは家の軒先などで子育てをするツバメですが,バードウォッチャーは夏鳥の季節になると心待ちにしている鳥がいます。今回は人気の夏鳥を紹介しましょう。


人気の夏鳥,1つ目はオオルリです。ヒタキ科に属する小鳥で,大きさはスズメよりも少し大きな16cmくらい,東南アジアで越冬し,日本には繁殖のために飛来します。名前に「ルリ(瑠璃)」と付いている通り,頭から尾にかけての背中側は深い青色をしています。一方,顔からのどは黒く,腹は白いので,コントラストの強い配色です。“青い鳥”ということで人気が高いのですが,その魅力は姿だけでなく,声も美しい鳥です。「ヒーリーリー,ジジッ」と聞きなされるさえずりは,コマドリやウグイスとともに「日本三鳴鳥」に数えられるほどで,オスは木のてっぺん,梢付近でその美しいさえずりを聞かせてくれます。丘陵地から亜高山帯まで比較的生息範囲が広く,特に渓流沿いを好んでいます。なお美しいさえずりと姿は雄成鳥の特徴で,雌や幼鳥は全身灰色の地味な姿です。


オオルリと並んで人気の夏鳥がキビタキです。オオルリと同じヒタキ科に属し,大きさはスズメよりも小さい13cmくらい,東南アジアで越冬し,日本で繁殖します。名前に「キ(黄)」が付くように,キビタキは眉やのどから腹,腰は鮮やかな黄色,顔や背中は黒,翼は白い斑の入った黒色で,こちらもコントラストのはっきりした配色です。「日本三鳴鳥」には入っていませんが,キビタキもさえずりが美しく,「ピチュリーピリリ,ピッコロロロ」と軽快な歌を聞かせてくれます。また自身のさえずりだけでなく,別の種類の生物の声をさえずりに取り入れることもでき,例えばセミのツクツクボウシの声がさえずりのレパートリーに入ることもあります。丘陵地から亜高山帯まで見られるという点はオオルリと同じですが,オオルリよりは平地寄りの環境でも見られ,近年では平地の竹林や都市部で繁殖したという記録もあります。キビタキも雌や幼鳥は全身灰色の地味な姿をしています。


姿も声も美しいオオルリとキビタキ,バードウォッチャーでなくても出会いたい鳥でしょう。確実に会いたいのであれば,4〜5月の丘陵地の広葉樹林に行きましょう。林内を歩いて探すときは,まずさえずりを予習しておくことが必須です。山の小鳥の発見はまず姿ではなく,声に気づくことが大半だからです。そしてさえずりが耳に入ったたら,キビタキであれば木の中間部分,枝葉の少ないすっきりした部分を丹念に探してみましょう。キビタキの黄色は林内でも割と目立ちます。1か所にずっと留まるタイプの鳥ではなく,さえずりながら転々と移動しますが,お気に入りの場所はあるようなので,動きを観察し,あまり動き回らず待つのもおすすめです。
一方オオルリの場合,さえずりが聞こえたら,まずは見える範囲の木のてっぺんを探すとよいでしょう。キビタキと違い,オオルリは木の梢で長い時間,1か所に留まって鳴くので,比較的見つけやすいです。ただ,木のてっぺんにいるため背景が空になることが多く,その美しい青色が黒く潰れて見えることも少なくありません。渓流沿いであれば谷を見下ろす林道や橋の上から見下ろす形で探したり,そういった環境でなければ,オオルリに気づかれないようにゆっくり,距離を取りながら移動し,背景を葉や山など,空以外の暗いものになるように位置を回り込めば,その美しい瑠璃色を見られるでしょう。
両種とも渡来した当初が最もよくさえずるために見つけやすいです。しかし季節が進めば繁殖に入ってさえずりが減るだけでなく,木々の葉も増えて林の中の見通しが悪くなり,探しにくくなります。「夏鳥」とは言いますが,梅雨入り前が観察の適期なのです。
5月以降,梅雨〜夏でも山間部では,オオルリやキビタキの姿を見かけることがあります。さえずりを聞くことはあまりありませんから,声から探すことはできませんが,山歩きの時にも「いるかもしれない」と気をつけていれば,偶然の良い出会いがあるかもしれません。




このようにオオルリやキビタキに会うには,春に標高の高い場所に行くのがセオリーですが,渡り鳥であるこの鳥たちは,移動途中に思わぬ場所に立ち寄ることがあります。それが街なかの公園や雑木林です。地域によって差が出ますが,だいたい4月中,遅くとも5月の大型連休前にまとまった林のある公園を早朝に歩いてみると,オオルリやキビタキに出会うチャンスがあります。サクラなどのあまり高くならない木に止まってくれれば,その姿や声をゆっくり観察することができます。しかし,これはあくまでも移動中の立ち寄りなので,滞在時間はかなり短く,たった一日しかいなかったというケースも少なくありません。早朝の公園に足しげく通うことが出会いのポイントです。
また,オオルリやキビタキは夏鳥ですので,春に南から渡ってくるのなら,繁殖が終えた秋には同じように南へと渡っていきます。このタイミングでも街なかの公園で見られる可能性があります。9月中旬から10月の間,ミズキなどの秋に熟す実が付く木の近くで待てば,出会いのチャンスが巡ってくるかもしれません。