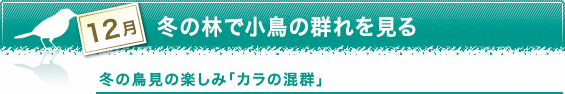
すっかり葉が落ちた冬の林,見通しの良くなった木々の間から,にぎやかな鳥の声が近づいてきます。最初は白くて小さなエナガの群れ,その後からはシジュウカラやコゲラなどがまるでエナガについていくかのようにやってきます。気が付くと,周りはたくさんの鳥たちに囲まれているような感覚になります。今回は冬ならではの鳥見の楽しみ「カラの混群」について紹介します。




「カラの混群」の「カラ」とはシジュウカラ科の鳥を指し,「混群」とは異なる種の鳥が1つの群れになることを指します。メンバーには先に挙げた3種のほかに,平地ではヤマガラやメジロが加わり,少し標高の高い地域ではゴジュウカラやコゲラ,ヒガラが入っていることもあります。ちょっと珍しいところではキクイタダキやセンダイムシクイなども見られることがあり,厳密にはシジュウカラ科の鳥だけで構成されることは少ないのですが,「主に冬に見られる,シジュウカラ科を中心にした小鳥の群れ」というイメージでいればOKです。
カラの混群に出会うとき,最初のきっかけになるのはたいていの場合,エナガの群れです。「ジュリジュリ」という特徴的な声が梢のほうからまず聞こえてきて,その少し後に混群の本隊が来ます。エナガは調査によると混群を作りたがる鳥なのですが,移動速度がほかの種よりも早いため,自然と先発隊になりやすい鳥のようです。
ちなみに,混群には1つの定義があって,それは「2種3羽以上,互いに25m以内,最短5分は維持され,同じ方向に30m以上移動する」というものです。異なる種で群れるということであれば,例えばシギ・チドリ類やカモ類も混群になりますが,カラの混群はほかの混群とは違い,かなり機能的なものになっています。ではなぜ冬の林で小鳥たちは群れるのでしょうか?




カラの混群をよく観察してみると,種類ごとに居場所が少しずつ異なります。例えばエナガは主に細い枝先,シジュウカラは枝や地面,ヤマガラは少し太い枝,コゲラは幹のあたりにいることが多いです。体の小さな鳥は枝先,大きな鳥は幹に近いところと,体のサイズによって1本の木でもすみ分けている印象です。これはそれぞれの鳥がどこで食事をするかが関係しています。身軽なエナガは枝先につかまったり,ホバリングをしながら小さな虫や木の実を探します。少し大柄なヤマガラは太めの枝の上で,木の実をくちばしで割って食べるところをよく見ますし,見つけた木の実を樹皮の間に隠す「貯食」をすることもあります。そしてコゲラはキツツキ類なので,樹皮の下などをつついて虫を探すのが得意です。シジュウカラは割と「何でも屋」で,枝の上で木の実を食べたり,地面の落ち葉の下から虫を見つけ出して食べたりします。つまり,それぞれの鳥が得意な場所と方法で食事をするため,群れていてもお互いに食物を取り合うことが少ないのです。そうはいっても,冬は食物が少ない厳しい季節,ヤマガラが貯食したものをシジュウカラが横取りするといったことも起きますし,ほかの鳥が食べ物を見つけた場所を自分も探索の参考にするといった抜け目ない一面もあります。群れているといっても,お互いに助け合って食物を探すのではなく,お互いの食事の邪魔をしない程度に一緒にいるということなのです。

鳥に限らず,群れる理由の大きなものは「身を守る」ためです。群れのメンバーの数が増えれば,より多くの目と耳で周りを警戒できます。カラの混群にも同じことがいえるのですが,ちょっと様子が異なります。先ほどから混群の中でエナガは先頭で動き,かつ枝先など割と上の空間にいることが多いと紹介してきました。これには身軽なので枝先のような場所でも採食に利用できるためでもありますが,実は「仕方なくそこにいる」という部分もあります。枝先のような場所は外から見えやすく,小鳥たちにとって恐ろしい敵である猛禽類のハイタカなどからも見えやすい位置です。できれば太い枝や幹といった,木の内側のいたほうが安全なのですが,そういった場所はヤマガラやコゲラといった体の大きな鳥が占めていて,入り込むことができません。実は混群のメンバーの間には「種間順位」というものがあり,それは体の大きさで決まります。体の小さなエナガは外に追いやられ,混群の警戒役をやっていることになるのです。エナガにしてみれば危険な群れの外にいることはデメリットなのですが,それでも混群の主要メンバーになっているのは,少しでも周囲を警戒する目と耳が多い環境にいたいからかもしれません。ちなみに,小鳥たちが猛禽類などの敵を見つけた際に発する警戒声は,異なる種でもよく似ており,混群の中で捕食者が近づいたことを知らせる共通言語として役立っているといえそうです。




