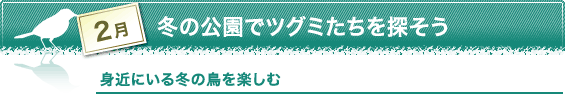
各地から寒波や雪の便りが届き,まさに冬本番を迎えています。前回のカモのときもお話したように,木々の葉が落ち,見通しのよい冬はバードウォッチングに適したシーズンです。カモの仲間は主に水辺で観察する鳥ですが,今回は林や公園といった陸地で見られる冬鳥の代表を紹介しましょう。
冬,公園の芝生広場や農地など,ちょっと開けた緑のある場所で,すっくと胸を張って立っているちょっと大きめの茶色の鳥がいたら,それがツグミです。少し近づいてみると,小走りに駆けて逃げるものの,あまり遠くまでは行かず,また同じ姿勢で立っています。都市公園のような身近なところでも見られ,立ち姿はよく目立ち,しかも「つぐみ」という名前は物語や歌,あるいは人の名前にも使われるので,一般的にも知名度の高い鳥です。


しばらく見ていると,ツグミは地面に飛び込むようにくちばしを勢いよく,しかもくり返し突っ込みます。これは土の中の昆虫の幼虫やミミズなどを探す行動です。また,木の実も好物で,特にカキにはよく集まっています。実はツグミは北海道など早いところで10月中旬,本州の平野部でも11月には繁殖地のシベリアなどから渡ってきていますが,渡ってきた当初は,ちょうど実りを迎えた木の実を樹上で食べるためあまり目につきません。冬によく見られるのは,木の実を食べ尽くし,地上で必死に食べ物を探している姿なのかもしれません。




ツグミを観察したら,目線を少し林や草むらに移してみましょう。よく目立つ枝や杭の上に,ツグミよりも小さな,お腹のオレンジ色が印象的な鳥が止まっていることがあります。その鳥が尾羽を振っていたらジョウビタキです。耳をすますと「タッ,タッ」という,舌打ちのような声も聞こえてくるかもしれません。このジョウビタキもツグミと同じく,日本で冬を越すために渡ってきた冬鳥です。ジョウビタキは先ほどのツグミと違い,オスとメスで大きく姿が違います。先に紹介したお腹のオレンジ色が印象的で,顔は黒く,頭の上が灰色なのはオスで,一方のメスは全身がほぼ茶色で,翼の部分に大きな白い斑があることが特徴です。メスは姿は地味かもしれませんが,目が大きく,くりくりとしたかわいらしい顔をしているので,バードウォッチャーに密かな人気があります。


もし身近なところでジョウビタキに出会う幸運に恵まれたら,あなたは次の日も,またその次の日もジョウビタキに出会えるかもしれません。ジョウビタキは冬に1羽ずつなわばりを作ることが知られています。つまり,同じなわばりの中であれば,同じ個体に日を変えて出会うことができるのです。このなわばりは,厳しい冬を乗り越えるために,食事をする場所を確保するという意味があり,渡来した当初は,そのなわばりを巡って同性・異性を問わず,激しい争いが起きることがあります。また,ジョウビタキは年によって冬越しの場所を変えないという研究もあります。もし今年ジョウビタキに会って,来年も同じ場所で見られれば,それは同じジョウビタキの可能性があります。


今回紹介したツグミとジョウビタキは,かつて「ツグミ科」という分類に入っていて,大きなツグミは“大形ツグミ類”,小さいジョウビタキは“小形ツグミ類”というグループ分けをされていました。現在は他のグループの鳥と統合された「ヒタキ科」の鳥に変更されたのですが,実はヒタキは漢字で「火焚き」と書き,これは先ほど紹介したジョウビタキの「タッ,タッ」という声が,火打ち石で火を起こす音に似ていることに由来するという説があります。つまりジョウビタキが「元祖ヒタキ」とも言えるわけで,ジョウビタキが昔から人の身近にいることがわかるエピソードです。
冬は今回紹介した2種類のほかに大形ツグミ類ではシロハラやアカハラ,小形ツグミ類ではルリビタキが日本に渡来します。ツグミやジョウビタキに比べると,少し木々の多い環境で見られる鳥ですが,身近な公園でも観察できる鳥ですので,ぜひ探してみてください。





